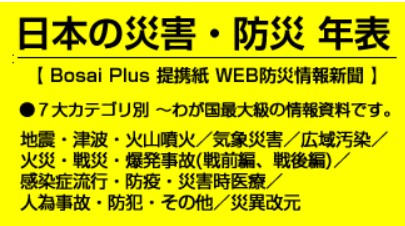能登半島地震の初動対応を検証してきた関係省庁のチームは去る6月10日、総理大臣官邸で開催された第7回「令和6年能登半島地震復旧・復興支援本部」会議で検証結果を報告した。能登半島の被災地では道路の寸断が多発し、被害の全容把握や救援物資の輸送が難航したことから、「半島防災」対策の強化が大きな課題……
報道によると、経済産業省は、能登半島地震で被災した自治体と連携し、電力使用状況のデータを被災者の居住証明として活用する実証実験を行うという。「罹災証明書の発行に必要な書類の代わりとして扱うほか、在宅避難する高齢者の見守りといった被災者支援に役立てる方向で検討、今月、参加する事業者の募集を開始し、石川県内などで導入したい考え……
今年の梅雨入りは全般的には遅れているようだ。6月14日頃までは梅雨前線は北上せず、本州付近は晴れて、厳しい暑さが続き、東北から九州にかけて広く真夏日(最高気温30℃以上)になりそうだという。猛暑日(最高気温35℃以上)が予想されている地域もあり、暑さに慣れていない時期だけに熱中症に警戒が必要だ。いっぽう、梅雨前線が停滞する沖縄は梅雨末期の大雨となっていて15日頃まで断続的に雨が降り、土砂災害や河川の増水、氾濫、低い土地の浸水に注意・警戒が必要……
初期消火に最も多く使用されているのは消火器だ。その成功率は75.7%(東京消防庁管内のデータ(2019年中)だが、使用率は18.9%と低い。消火器が必要なときに十分活用しきれていない原因としては、「重い、大きい、放水時間が短いなどのほかに、平時の置き場所に困る、使用時に噴射物(粉末や液剤)が飛散し消火箇所周辺が汚れる」などの問題があるのだという。そこで――
内閣府・国土交通省では、地域で発生した災害の状況をわかりやすく伝える施設や災害の教訓を伝承する活動(語り部、祭り、防災教育など)を「NIPPON 防災資産」(以下、「防災資産」)として認定する制度を新たに創設した……
気象庁では、2022年6月から、線状降水帯による大雨の可能性がある程度高いと予測できた場合に、半日程度前から気象情報においてその旨を呼びかけている。この呼びかけについて気象庁は5月15日、これまでは全国11のブロックに分けた地域(地方単位)を対象としていたが、2024年5月28日9時から、府県単位を基本に、対象地域を絞り込んで呼びかけを行うとした……
日本災害ロボットレスキューフォース(JRRF=JAPAN RESCUE ROBOT FORCE、東京都港区。以下「JRRF」)は、国内初の災害対応ロボット派遣団体として、令和6年能登半島地震の被災地支援を目的に救援活動を開始すると発表した。JRRFは最新のロボット技術と専門技術を活用し、迅速かつ効果的な災害対応を通じて、救助と復旧作業の質を向上させることをめざす……
直近の報道に政府(首相官邸:小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会)が、災害時のドローン活用を拡大する方向で最終調整に入ったというものがあった。「医薬品や食料品など支援物資の輸送であれば、飛行禁止空域でも許可を得ずに飛行できる仕組みの規制緩和を検討しており……
自衛隊は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震発災時における災害対処能力の向上を図るとともに防災関係機関、米軍及び豪軍との連携を維持・強化し、国民の安全と安心の確保に資するためとして、5月20日~24日の5日間、「令和6年度自衛隊統合防災演習」を防衛省市ヶ谷地区その他演習参加部隊等の所在地などで実施した……
防災士研修センターは「防災士制度」発足以来、全国各地で年間80回以上の研修を実施し、自治体や企業。個人でご参加された多くの受講生から高い評価と信頼を頂いております。防災士研修受講修了者のうち、約半数の方が当センターの研修を受講されています……
令和6年(2024年)能登半島地震からの創造的復興に向けた道筋を示すため、石川県は、被災地の住民へのヒアリングや、アドバイザリーボード会議での有識者からの意見も踏まえながら、「石川県創造的復興プラン(仮称)」を策定することとしているが、去る5月20日、同プランの案をとりまとめ公表した。県では引き続き、調整を進めながら策定を進めるとしている……
普段は食品の収納容器として……いざという時には”水だけで”温め可能な加熱容器に! 収納も温めもこれ一台でOK! 災害備蓄の定番となった備蓄食品などを日常使用しながら回転させる「ストックローリング」に、日用品として毎日手に取って便利で気軽に使える「あったかフードボックス」が登場……


」より-560x316.jpg)
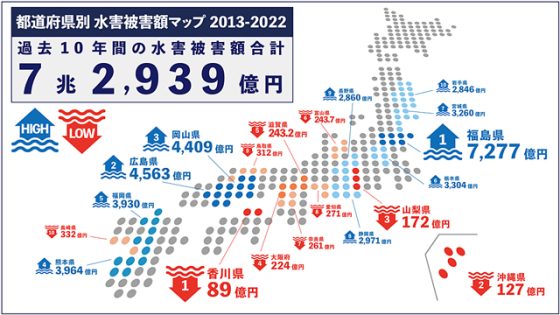

-560x348.jpg)

の空撮写真(石川県観光公式サイトより)-560x314.jpg)