防災士との共創 防災士と行政をつなぐ“機能づくり”が重要
共助にも限界?…
一般防災士と公的補償を付ける防災士との棲み分け制度設計も
本紙3月15日付け記事「防災科研『防災士との共創の進め方』を議論〈前編〉」に引き続いて、防災科研「災害レジリエンス共創研究会」討論会より「防災士の活躍による日本の防災力向上の可能性〜防災士との共創の進め方〜」の「続編『パネルディスカッション』」の概略をお届けする。

パネラー:寶(たから)馨・防災科研理事長、室﨑益輝・日本防災士会理事長(神戸大学名誉教授)、丹野 淳・福島高専都市システム工学科助教、李 泰榮・防災科研社会防災研究領域災害過程研究部門副部門 長、司会は奥村奈津美さん(防災士、防災アナウンサー)
●防災士制度の課題
社会・法整備、防災テクノロジーなどの変化のなかで、防災士資格が”永久資格”である(更新制度がない)ことについて――
寶(たから)氏は「防災分野のDX化については防災科研の研究成果アップデートをフォローしてほしい」、室﨑氏は「”上級防災士”などランクづけが議論にはなっているが、防災士創設の趣旨は地域に最小限の防災リテラシーを持つ人を増やすこと、裾野を広げることなので、資格の更新は意識していない。スキルアップは一種の資格更新とも言えるし、頂上を高くすることは次のステップかもしれない」と述べた。
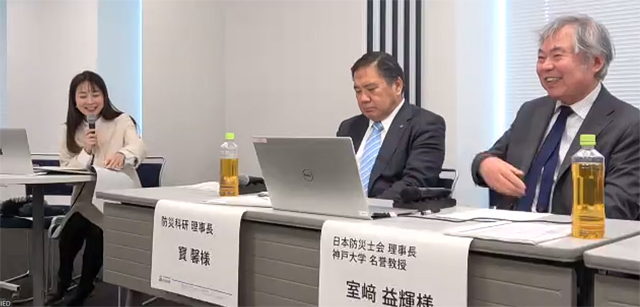
丹野氏はいわき市の例として「行政の補助を受けて防災士資格を取得しているので基本的に登録防災士。いまその活用法の議論段階で、例えば地区防災計画づくりをしたい人、語り部をしたい人などニーズに応じてスキルアップを図っている。災害時の避難所開設では登録防災士の召集になる可能性もある」と発言。
李氏は「防災士の底上げを図り、裾野を広げることは必要。ただ例えば消防団や水防団は非常勤特別職の地方公務員であり、なにかしらの対価が出る。災害時に負傷あるいは死亡した場合は補償が出る。しかし、防災への志をもとに行政の防災対策に協力を求めるのであれば、なんらかの補償に向けた制度設計が必要ではないかと考えている」とした。

これを受けて室﨑氏は、「行政の支援を受けて防災士資格を取得する人が増えているが、それはとても重い意味を持っている。市民の税金のお陰で得た資格なので、市民に返す責任がある。だからそれだけの責任を返しているかが問われる。しかし、その責任を負うのは本人の責任かというとそうではなくて、税金を出す側の責任。税金で市民を防災士にしたら、行政は防災に貢献する場、社会貢献する場をつくらないといけない。そこに官民連携が生まれるけれども、現状は、貢献の場づくりをおろそかにしている行政が多い」。
続けて李氏は「最近、国の国土強靭化計画のなかで防災士の活動が多く記載されるようになってきた。防災士の活動としては、国や自治体がつくる法的な防災計画のなかで、防災士に公務的に活動してもらうことで、十分な補償もクリアできる」とした。
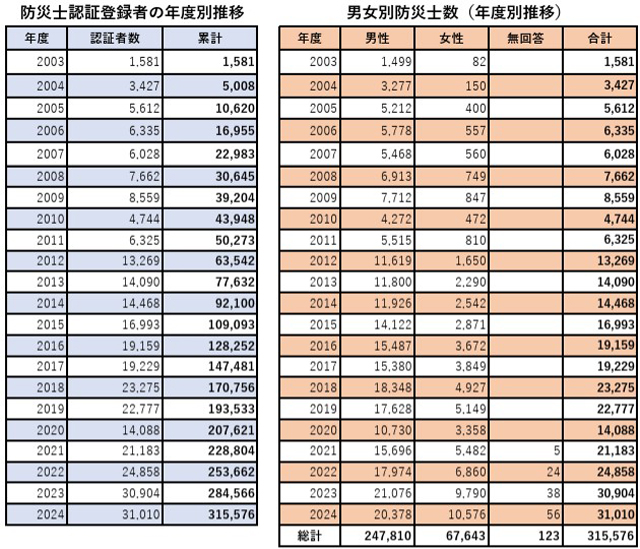
●防災士へのさらなる期待とは
丹野氏は「いわき市の事例でおもしろいのは、”運防会”という運動会x防災のイベントがある。地域に日常から防災を採り入れるということは重要」。
室﨑氏は「行政と防災士をつなげる仕組みが必要。そういった”つなぐ機能”を持った人・組織が現状では機能できていないのでは。だから、孤立する防災士もいる。孤立しているのはその人が悪いのではなく、つなぐ取組みができていない。行政がその役割をつないでくれることを期待するが、防災士自身がまずはコミュニティの一員として受け入れられることが前提だ」。
李氏は、「気候変動で災害の激甚化があるなか、また少子高齢化、人口減少下で、私は共助にも限界が見えてきていると考える。そこで、一般防災士の広がりの横軸と、タテ軸としての専門性の高い、公的補償を付けられる防災士との棲み分けの制度設計を研究していきたいと考えている」。
寶氏は、「福島高専のような教育機関での防災士の取組みはすばらしい。大学などでも防災講座を通じて防災士資格取得をめざすところが増えている。防災士の基本理念に「自助・共助・協働」があるが、「協働」がなかなか進んでいないという印象があり、防災科研としてはその協働を促進していきたい」とした。
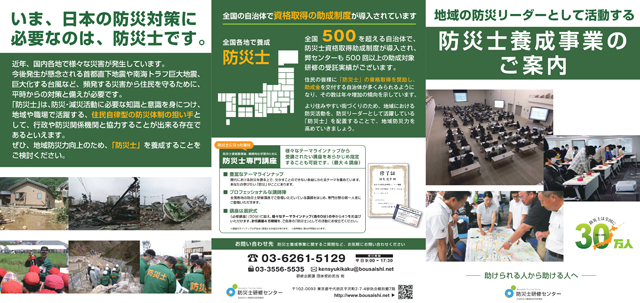
〈2025. 04. 05. by Bosai Plus〉
https://bosai-plus.info/

